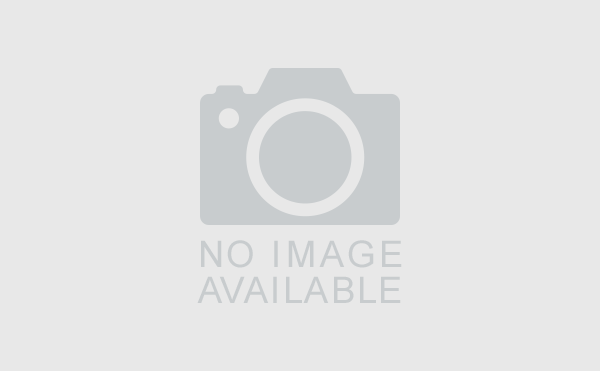県が「つや姫」栽培マニュアル改訂版 地力に応じ施肥量増も
トップブランド米を目指す県産水稲品種「つや姫」の栽培マニュアルの改訂内容がまとまった。2010年秋の本格デビュー以降、高品質、良食味米として高い市場評価を得る一方、10、11年産と続けて収量が指標値に及ばないといった課題が出たことを踏まえ、基本技術の順守に加え、作付けする土地条件に応じて施肥量の増加を認める点が特徴。県は各地で開く生産者研修会を通じて新マニュアルの周知徹底を図る。
県は10年3月、ブランド化戦略の一環で、品質や食味にばらつきのない「つや姫」を生産するため栽培マニュアルを冊子にまとめた。適正収量、穂数などの基本指標や、生育過程での草丈、茎数、葉色の濃淡具合の目安の他、地力を高めるために与える肥料の量や施す時期といった細かな技術ポイントを明記した。
新マニュアルについて県生産技術課は「基本技術の重要性を再確認してもらうことと、これまで一律的だった施肥量を土地条件によって増やせるようにした」と改訂部分を説明する。
基本技術面では、生産者に土壌分析を行うよう促し、養分のバランスが取れた土づくり、適期の田植え作業、適正な植え付け株数を従来同様心掛けるよう強調。肥料の扱いでは、稲の生育状況などをみて、生産者が必要だと判断した場合、これまでの標準量に一定量をプラスして与えられるようにした。ただし、窒素成分を多く与えた場合、生育が進む一方、食味が落ちる影響も想定されると言う。同課は「つや姫の特性を生かす栽培法はこれまで通りが基本。だが作付面積の拡大に伴い、地力に高低差がある水田が出てくる可能性があり施肥量の上限を緩和した」と話す。
「つや姫」の平均収量の指標値は、10アール当たり570キロ。高い1等米比率を記録した10年産つや姫の平均収量は527キロにとどまった。続く11年産は平均収量がまだ確定していないが、庄内地域を中心に極端に少なかった。この現状を踏まえ、県は収量の安定化に向けた栽培マニュアルの見直し作業を進めていた。
2012年02月14日 山形新聞