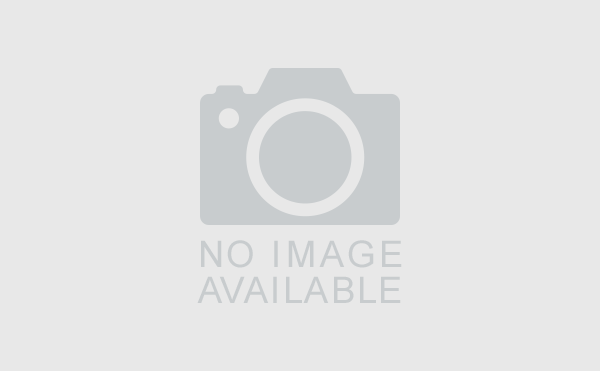コシヒカリを超えろ! 新ブランド米「つや姫」の挑戦
平成10年。山形県鶴岡市の水田農業試験場でプロジェクトは立ち上がった。4年に待望の新品種はえぬきを世に送り出していた山形だが、米価の低迷も向かい風になり、「次」への模索が始まっていた。
「はえぬきを山形に特化するため、種子を供給したのがわずか5県。この“囲い込み作戦”が、結果的に認知度を低下させたかもしれない」と、県産米ブランド戦略室長の武田一夫はいう。
はえぬきは8月上旬に、コシヒカリは下旬に出穂(しゅっすい)期を迎える。県が狙ったのはその狭間(はざま)だった。水田農業試験場水田研究科長の結城和博は「中旬に出穂期を迎える稲を開発すれば、はえぬきと共存できる」と新品種の照準を絞った。
“母方”に山形70号、“父方”には東北164号という良種が選ばれた。勾配と選別が繰り返され、4年後の14年に1つに絞り込んだ時には、サンプルは10万にものぼった。ほ場がある鶴岡市は14年に冷害、15年には潮風害に見舞われたが、つや姫はびくともしなかったという。
実験的な作付けが続き、22年には商業ベースでの本格的な作付けが始まった。選ばれた農家は2500人(2500ヘクタール)。「トップクラスの農家の方々を選別した。失敗は絶対に許されなかった」(武田)
寒河江市の農業、土屋喜久夫もそのひとり。土屋には実は強い思い入れがあった。地元の農協で水稲部会長をしていた16年、他品種の打診があった。「山形ですごい米ができるという話がある。もしできたら戻れなくなる。我慢しよう」。土屋は、その時を待った。
米作りのプロを自任する土屋だが、妻は試験的にできた最初のお米に、「大きい粒で、いいできだね」と喜んだ。「やった、と思ったね」(土屋)
そして今-。山形は今年、記録的な猛暑に見舞われ、農作物も大きな被害を受けた。水稲も1等米の比率を下げるなか、つ姫は98%という驚異的な数字をたたき出した。「暑さにも強い」。猛暑が逆に、つや姫の評価を上げた形になった。売れ行きも予約だけで半数以上が埋まるなど次々と常識を覆している。
結城は、つや姫が持つ潜在能力の高さに驚く。「どんな天気になっても、自ら成長を急がないんです。コシヒカリは暑いと実りを早めますが、つや姫はスピードアップしない。猛暑にも強いとわかったのは、たまたまですが…」。ブランド力に背中を押され、急きょ作付面積を広げることが決まっている。
米価引き下げやTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)など農業を取り巻く環境は厳しさを増す。つや姫は逆境を切り開く可能性も秘めている。=敬称略
■うまさの秘訣は「つや」
水田農業試験場と慶應義塾大学先端生命科学研究所(鶴岡市)の共同研究によると、実際に炊いた130サンプル(28品種)の米を解析した結果、つや姫はコシヒカリに比べ、グルタミン酸やアスパラギン酸といった代謝物が多いことが判明した。
試験場の後藤元(はじめ)研究員は「これら2つのアミノ酸は他の食品でもおいしさに関わっている例が報告されています」と話す。
先端研の富田勝所長も「つや姫はうま味の成分が多く、嫌悪感を抱く成分が少ない、バランスの良さが明らかになった。すべての成分が多い品種はあったが、バランスの良さがつや姫のおいしさの秘密である可能性が高い」と太鼓判を押している。